第2話 からの続き
ロードキングを買って最初に訪れた自分の誕生日に僕は彼女からヘルメットを貰った。それまで使っていたヘルメットは量販店で購入した安物。いずれちゃんとしたものを買おうと思っていたから、それまでの繋ぎのつもりでいた。実は僕が欲しかったヘルメットは少し高かったので手が出なかったのである。すると、その欲しかったヘルメットを彼女がプレゼントしてくれたのだ。これはそんな冬の日の話。
***
昼前に出発して西湘バイパスから真鶴道路を抜け、海沿いの道を熱海の先まで走る。カラカラに乾いた空気に響く排気音が心地良い。風は無いから太陽が出ていればそれほど寒くはない。途中、信号で陽だまりに停まるとポカポカと暖かい太陽。思わず空を見上げると、色は薄いけれど透き通るようなブルーの空。真っ青な絵具に純度の高い透明なクリアを混ぜて伸ばしたような色だ。真夏に比べると明らかに浅い角度で輝く太陽がキラキラと照らす、逆光の海を左手に見ながら伊豆半島を南下する。
最後尾を走る僕は実は目的地を知らない。先頭を走るテツが「うまい海鮮丼が食える店に連れて行く」と言ったので、腹を減らして彼を追いかけているだけだ。 テツの後ろにはヒロ、そして自分。いつもの三人。信号で停まる度、前の二人はバイクを並べて何かを喋っている。僕は二台のバイクの真ん中あたりにフロントタイヤを浅く突っ込んでそれを見守る。排気音に掻き消されて彼らが何を喋っているのかはまったく分からないが、なんとなく二人の身振り手振りの会話を眺めているだけでよかった。
海沿いの道が小さな町に入ると、先頭を走るテツは少しスピードを落とした。もうすぐ午後一時半を回ろうかというその時、僕は自作のハラ減った音頭を唄っていた。黄色の点滅信号が小刻みに並ぶひっそりとした季節外れの観光地に人の気配はない。辺りを見回しながらゆっくりと進む彼の後ろで何かを待つ。すると小さな交差点の手前で、左ウインカーが静かに点灯を始めた。ああ、やっとメシだ…。
座敷の縁に腰をかけ、三人で同じように重いブーツを脱ぐ儀式。それが終わると大袈裟に着込んできた上着を一枚一枚脱いでハンガーに掛ける。座布団の上に胡坐をかくと、テーブルの上に熱いお茶の注がれた湯飲みが三つ。魚偏の漢字がぎっしりと並んだ湯飲みを、三人それぞれ冷えた両手で優しく包む。
旬の魚と、ウニとホタテが乗った海鮮丼は絶品だった。ほんのり暖かい酢メシが盛られたどんぶりを、左手のひらで持ち上げた時の指先がじんわりと温まる心地良さが堪らなかった。食事が終わっても動く気にならなくて、そのまま何杯かのお茶を貰いながら他愛のない話をしながら過ごした。どのくらい経ったのだろう、 重い腰を上げて外に出ると太陽の位置がすっかり変わっていた。西に傾き始めた陽射しは儚く弱く、吹く風は冷たくなり始めていた。
「よし、帰ろう!」
まるで迫り来る何かから逃げるかの様に、帰り支度をして来た道を引き返す。
「海老名、寄る?」
高速に乗る手前の信号でテツが訊いてきた。東名高速、海老名サービスエリア。西に行った帰りには、いつもそこに寄るのがお約束だった。
「ゴメン、今日はそのまま帰るよ。実はオレ、今日誕生日なんだ」
渋滞が始まりかけた夕方の東名高速をすり抜けながら走る。海老名サービスエリアに滑り込んでいく二台のロードキングに手を振ると、僕は一人になった。東京料金所を過ぎた辺りでポケットに突っ込んだ携帯電話を手探りで探し出し、リダイヤル履歴から彼女の名前を探して発信ボタンを押すと、そのままポケットに押し戻した。
「夕方走りながら電話するから、着信があったらお風呂にお湯入れといて。あ、あと、なるべく早く帰るから」 今朝、そう言って出掛けてきたのだ。
薄暗くなり始めた頃から急激に気温は下がりはじめ、カラダはすっかり冷え切っていた。今まさに自宅の風呂場で勢い良く出ているであろう、蛇口からお湯が溢れ出るイメージが頭に浮かぶ。悴んだ手の感覚は鈍り、ブーツの中のつま先は少し痛い。冷たい空気のカタマリに時速100キロでカラダごと突っ込み続けるという行為に少しの理不尽さを感じながら、少しづつ湯船にたまる熱い湯を想う。 寒いけど、もっと冷えろオレのカラダ。もうすぐ熱い風呂にハイレルゾ。
首都高に入るとまるで何かと闘っているかの様に先を争うクルマたち。この獰猛な群れをやり過ごしながらも帰路を急ぐ。なんとか家のそばまで辿りつき、自宅の駐車場に滑り込んだ。熱海の先からノンストップで走り続けてきたせいか、スタンドを出そうとする左足にもはや感覚はなかった。
「ただいまー」
「おかえりー!」
ぴょんぴょんと部屋の奥から飛び出してきた彼女は、限界まで冷たくなった僕の頬をニコニコしながら触りたくり、「お風呂沸いてるよ」と言う。玄関先で上着を彼女に渡し、そのまま風呂場へ向かう。スナップボタンのシャツをビョビョっと開き、ベルトを外してジーンズから足を引っこ抜き、強引に靴下を剥ぎ取りながら、下着をポイポイっと洗濯カゴに放り投げると、湯気の上がる湯船にドボンと浸かった。
ウウウ…。声にならない声が思わず洩れる。凍りついたカラダが解凍される至極の時間だ。カラダの至るところから「ピシッ、ピシッ!」と、亀裂音さえしそうな錯覚に陥る。少し手足が緩んだところで今度は鼻をつまんで仰向けに湯船に潜る。目を閉じたまま見上げる天井。あまりの気持ちの良さに悶絶。そして首までお湯に浸かったまま手足の指を動かして、じわじわと感覚が戻るのを待つ。
カラダから湯気が上がるほど温まると風呂を出た。リビングをちらりと覗くとテーブルの上には記念日然とした料理が並び、その中央にはハートのケーキが置かれていた。急いで髪の毛を乾かして食卓に着くと、「お疲れさま」と言って冷えたビールが出てきた。どんな季節でも風呂上りのビールは最高だ。
いつもより豪華な食卓には彼女の手料理がズラリと並ぶ。どれもこれもが好物ばかりだ。ビール片手に端から手を出し、「旨い!」を連発していると、彼女は別の部屋に何かを取りに行った。何食わぬ顔で再び現れた彼女の顔は、奥歯の奥で笑っている。そして後ろ手に大きな紙袋を持っていた。彼女がこっそり家に持ち込んでいたその紙袋から四角い箱が出てきた瞬間、僕の心臓は少し飛び上がった。包装紙に包まれて中身は分からないけれど、その絶妙なサイズの箱はヘルメットであることを瞬時に予感したからだ。あれは多分ずっと欲しかったヘルメット。
恐らく満面の笑みだっただろう僕は、彼女から箱を受け取るとクルリと回して裏側で包装紙を留めてある5センチほどのセロテープを指先で縦に裂いた。包装紙を開くと白い箱に青の文字でアルファベットが沢山書かれている。そしてそこには雑誌で見慣れたヘルメットのロゴマーク。
「ありがとう!」
もしかすると僕は少し涙目になっていたかもしれない。そのくらい嬉しかったのだ。
「被ってみてもいい?」
夢中で梱包を解きながら訊いてみた。
「もちろんいいわよ」
そう言う彼女の声を聞きながら、そういえば去年も同じことをしていたのを思い出す。確か去年は着ていたシャツを脱ぎ捨てて、貰ったばかりのシャツとネクタイ姿で彼女と一緒に並んで姿見に映ってみたのだった。今年も去年と同じように、貰ったばかりのヘルメットを被って彼女と一緒に姿見の前に立ってみた。部屋の中で笑顔のヘルメット姿。今年の僕はとてつもなく間抜けだった。
ハーレーに乗り始めたくらいで本当に何かが変わるのだろうかと不思議だったけれど、気付けば僕は真冬にも関わらずバイクで出掛けるようになっていた。それに少なくとも彼女が僕のヘルメットを買いに行くという状況は、明らかな変化である。今までは渋谷とか新宿に買い物に行っていた筈の彼女が、今年は何処かのバイク屋に一人で行ったのだから。ヒールの高い靴にファーの付いたコートを着て見知らぬバイク屋に足を踏み入れる姿は、明らかに異様だ。しかしそれを受け入れてくれた彼女に、僕は感謝せずにはいられなかった。だから今度は僕が彼女のヘルメットを買いにいこう。そして彼女を後に乗せて何処かへ走りに行こう。もうすぐ、待ち焦がれた春が来るから。
***
子供の頃、私の誕生日ケーキはいつもハートの形をしていました。ハート形のチョコレートケーキ。でも友達のお誕生日会にお呼ばれすると、みんなのケーキは丸型でした。丸い生クリームのケーキ。
「お前は他の子より親に愛されているからハートのケーキなんだよ」
父親にそう言われていたので、ずっとハートのケーキをとても誇らしく思っていました。ただ味に関しては生クリームの方が好きだったので、ある年、母に相談してみました。
「ねえ、たまには生クリームのケーキも食べてみたい」
「そう?ハートのケーキの方が安いのよね」
母曰く、バレンタインデーの翌日、ハートのケーキはとても安く買えるのだそうです。
私の誕生日は2月15日。
ハッピーバースデー、フォー・ミー… 。
第4話 へ続く











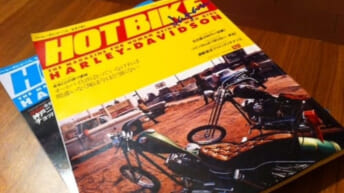



コメントを書く